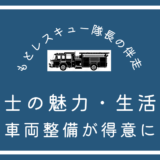消防士になりたい、消防の仕事に興味があるけれど…

訓練って厳しいよね?

消防士はロープを結んだりするのが得意なの?

どんな訓練をしているか知りたいな…
と想いや悩みを巡らせているのではないでしょうか?
この記事では、これらの想いや悩みを
『東京消防庁もとレスキュー隊長』の『バリー』が今までの経験から解説・アドバイスします。
最後まで読んでいただけたら、ロープワークの基本がざっくり分かると思います。
ちなみに私は、

消防士は「やりがい」があって最高!
プライベートも充実させてくれて感謝!
って想っている幸せものです。
消防士になりたい、興味がある方にとって、この記事が消防の世界に足を踏み入れる『きっかけ』になってもらえると嬉しいです。
命を繋ぐロープ
消防士は、ロープで様々なことができます。
住宅火災の2階で逃げ遅れた人を三連はしごとロープを使って、窓やベランダから地上に救出したり…
燃えている建物内に入るときは、隊員同士をロープで繋ぎ、不測の事態の時にそのロープを伝って逃げてきたり…
高いところからロープを垂らして、それ伝いに降りていき要救助者に接触したり…
マンションのベランダから単はしご(長さ3mの短いはしご)を使って登る時、命綱として使ったり…
その他にも様々な場面でロープを使います。
共通して言えることは、ロープの先には「人の命が懸かっている」ということです。
そのため、消防士にとって「ロープワーク」の訓練は欠かせません。
【ロープについて解説】
素材:ナイロン製
強度:2800㎏
直径:12㎜
長さ:10m、20m、30m、50m、100m
ロープは200mで納品されるため、これらの長さに切り分けて使用。
また、5mくらいに切り分けた短いロープを小綱(こづな)と言います。
ロープで結ぶことを結索(けっさく)と言い、その種類は3つあります。
①結着(けっちゃく):ロープを人や物に結び、しっかり固定すること
「巻き結び」「もやい結び」「ふた回りふた結び」「プルージック結び」など
②結節(けっせつ):ロープの間に輪や節を作ること
「フューラー結び」「ちょう結び」「二重もやい結び」「三重もやい結び」など
③結合(けつごう):ロープの両端や違うロープ同士を繋ぎ合わせること
「本結び」「ひとえつなぎ」「ふたえつなぎ」など

消防学校に入校したら、教官が丁寧にロープワークを教えてくれます。
教官の教えを見てるだけでは、結索技術は身につかないので、毎日ロープを触り、個別訓練をしていくことが大切です。
よく使う結び方
この記事では、消防士が災害現場でよく使う結索を3つ紹介します。
こられの結索は、ロープワークの基本となり、応用的な結索や救出方法に発展していくものです。
消防士になる前にできるようになっていると訓練にスムーズに入っていけるでしょう。
巻き結び
消防士が最も使う結索です。
種類は結着。
利点:結びやすい、締め付けやすい、解きやすい。
欠点:引かれる方向によっては、結び目が回る可能性がある。
三連はしご(長さ9m)を住宅2階のベランダに架ていした時、はしごが倒れないようにはしごとベランダ手すりを結着したり…
投光器(ライト)のコードを上階に伸ばし、余長(余った長さのコード)が下に落下しないよう結着したり…
資器材を上階へ搬送する際、上階から地上へロープを垂らし、そのロープの先端で資器材を結着し、つり上げたり…
様々な用途で使います。

三連はしごの引綱で固定する方法も巻き結びです。
この訓練のエピソードを書いた記事がありますので下にリンクを貼っておきます。
 訓練エピソード③《三連はしごの基本》
訓練エピソード③《三連はしごの基本》
もやい結び
巻き結びと同じくらい使う結索です。
種類は結節。
利点:結びやすい、解きやすい、輪の大きさが変わらない。
欠点:人や物に締め付けにくい(巻き結びに比べて)
火災建物に入る時、30mロープの先端にもやい結びを作り、その輪に隊員の命綱をつないだり…
逃げ遅れている人をはしごで上階から下階に降ろす際、命綱として胸部に結索したり…
救助活動で救助ロープ(30mロープをダブルで使用するもの)の先端にもやい結びを作り、その輪に救助資器材(担架やハーネス)を繋げて要救助者を救出したり…
様々な用途で使用します。
プルージック結び
基本結索の一つだが、応用的な使い方ができる便利な結索方法。
種類は、結着。
利点:解きやすい、結び目の移動と固定が行える
欠点:ロープがきれいに並んでいないと利点を活かせない
火災建物上階にホース延長する際、ホースの重みで地上に余長が落ちてしまうのを防ぐために結索する。(プルージック結びだとホースの余長の調整が容易で、余長が落ちないよう固定することもできる。)
その他にも、ブリッジ線や懸垂線の支点のバックアップにプルージック結びを応用的に使用します。
 | 価格:4290円 |
結索訓練
結索訓練は、消防学校の訓練で頻繁に行われます。
消防署でも、小隊長(指揮者)が隊員に指導する形で行います。
実施方法は、隊員数人が横に列を作り、指揮者になる人が正面に立ちます。
小学校の運動会で体操の体形に開いた生徒が前に出た代表者を真似て体操をするイメージです。
指揮者が「巻き結び用意!」と言うと…
隊員が「よし!」と答えるとともに、ロープの端末を持ちます。
指揮者が「はじめ!」と言うと…
隊員自らの腕に巻き結びを作り「巻き結びよし!」と言います。
指揮者が隊員の結索を確認してから「巻き結び解除!」と言うと…
隊員が「よし!」と答えるとともに巻き結びを解除します。
この一連の流れを様々な結索方法で訓練を行っていきます。
結索で大切なこと
結索で大切なことは大きく3つあります。
1つ目は、しっかり締め付けることです。
締め付けがあまいと荷重がかかった時に結索部分が緩んできて、摩擦が生じロープを痛めることになります。
最悪の場合、ロープがほどけたり、切れてしまいます。
それを防ぐためにもしっかり締め付けましょう。
2つ目は、荷重がかかる方向(引かれる方向)を意識して結索することです。
結索して、ロープに荷重がかかると引かれる方向に結び目が動いてしまうことがあります。
これも摩擦を引き起こし、ロープを痛める原因になるため、荷重がかかる方向に結び目を作る必要があります。
3つ目は、結び目の端末はしっかり出すことです。
結索して、ロープが余る側を端末と言いますが、この端末が短いと荷重がかかった時や何かと接触してしまった時に結索がほどけてしまうことがあります。
東京消防庁が使用するロープは、直径12㎜のため、端末は10㎝以上出すことを原則としています。
各結びのリンク動画(YouTube・結びの教科書)では、結索の最後に半結び(端末を一回クロスさせて結ぶ)を作成しています。
これは、ロープの端末が抜けないよう二重の安全措置がされているのです。(東京消防庁の結索も半結びを作成します。)
結び目の端末を10㎝以上だすことを心掛けましょう。
まとめ
災害現場でロープなしでは、消防士の活動は成り立ちません。
ロープは、要救助者の救出、隊員の安全確保、資器材の投入など、本当に良く使います。
そして、ロープの先には人の命が懸かっているのです。
燃えさかる炎…
熱さで恐怖を感じている場面…
助けを求める声…
慌てて手が思い通りに動かない場面…
どんな状況においても責任を持って結索しなければなりません。
それには、日々の結索訓練が大切です。
部隊全体で訓練をすることも大切ですが、個別に訓練をすることの方が大切です。
自分が苦手な結索を集中して行うとか…
たくさんの種類の結索を行うとか…
時間を決めて、できる限りの結索をするだとか…
自分で訓練メニューを決めて行っていくのです。
そして、毎日その訓練を習慣化していきます。
そうすれば、どんな状況でも手が自然に動いてくれるはずです。

消防士が訓練や災害現場でロープワークを駆使している姿は勇ましいです。
私たちの誇りでもあります。
ぜひぜひ消防の世界に!
 | 2026年度版 東京消防庁 科目別・テーマ別過去問題集(消防官1類) [ TAC出版編集部 編 ] 価格:2530円 |
 もとレスキュー隊長の伴走
もとレスキュー隊長の伴走