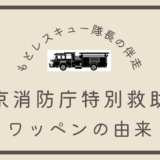消防士になりたい、消防の仕事に興味があるけれど…

ホースを伸ばして放水する訓練はやっているの?

放水する時に消防士が持っているいるものは何?

訓練のエピソードが知りたいな…
と想いや悩みを巡らせているのではないでしょうか?
この記事では、これらの想いや悩みを
『東京消防庁もとレスキュー隊長』の『バリー』が今までの経験から解説・アドバイスします。
最後まで読んでいただけたら、放水訓練の内容がざっくり分かると思います。
ちなみに私は、

消防士は「やりがい」があって最高!
プライベートも充実させてくれて感謝!
って想っている幸せものです。
消防士になりたい、興味がある方にとって、この記事が消防の世界に足を踏み入れる『きっかけ』になってもらえると嬉しいです。
目次 非表示
筒先(つつさき)
ホースの先端には、筒先が付いています。
筒先には、数種類あり、都道府県によって配置されるものが違います。
東京消防庁がよく使うのは、「21型ノズル」と「ガンタイプノズル」です。
筒先の解説
【21型ノズル】
筒状になっていて、両手で持ち、放水圧力で手を離さないように注意しながら、左手でノズルを操作することができる。
ノズル:放水をストレートタイプ、噴霧タイプにすることができる。
管そう:放水する際に持つ所。東京消防庁の管そうには、主に21型ノズルが付けられている。
主な特徴は、同じ管そうで先端を筒状のスムースノズルに変えることができ、大量の水を出すことができる。
そのため、燃えている建物の外から大量に水を掛ける時に有効。
【ガンタイプノズル】
本体下部に取っ手がついていて、それを右手で握り、左手で放水コック、流量切替ダイヤル、ノズルを操作することができる。
放水コック:水を出したり、止めたりすることができる。
流量切替ダイヤル:水が出る量(流量)を4段階に調整することができる。
ノズル:放水をストレートタイプ、噴霧タイプにすることができる。
主な特徴は、携帯性と操作性がよく、放水による圧力を若干抑えることができる。
そのため、燃えている建物の中に入っていく時、放水しながら前進することがしやすくなる。

東京消防庁では、この2つの筒先の特徴を活かすため訓練を行っています。
今回の記事では、私が消防学校で行った訓練を2つを紹介します。
21型ノズルによる放水訓練
私が消防学校の学生だった頃の体験した放水訓練の話です。
使った筒先は、「21型ノズル」
消防学校の敷地内でポンプ車からホースを40m延長し…
「放水はじめ!」と機関員に合図する。
機関員が放水コックを開き、ホースに水がのる。
平らになっているホースが蛇行し、膨らんでいく。
その様子を見て放水に備える。
前のめりになって、しっかり構える。
「プシュー!ジャーーー!」
空気が抜ける音とともに水が勢いよく放水される。
はじめは、ホース内の空気が含まれているため、放水が断続的に噴霧状になり安定しない。
しばらくすると空気が抜け、きれいな棒状の水になり放水されていく。
放水の圧力が全身にのしかかる。
さらに前のめりに構えるが、下半身の踏ん張りが不安定だ。
それでも、足に力を入れ何とか踏ん張る。
ひらすら耐える時間が続く。
しだいに管そうを握る握力が弱ってきた。
その様子を見たからか…
教官が「筒先補助!」と指示した。
学生の一人が私の後ろに付き、ホースを持ち前に突き出した。
放水圧力が二人に分散される。
何とか耐えられそうだ。
そこに教官から
「放水やめ!」
と指示があり、機関員が放水を停止する。
一気に放水圧力が弱まり、ホースから水が抜けていった。
私が筒先を持つ番が終わり、5人でローテーションする。
この日は、1人3回筒先を持つことができた。
1回目より2回目、2回目より3回目の方が筒先を上手く保持できた感じがした。
体力的には後半の方が弱くなってるはずだが…
やはり筒先を持つ姿勢や管そうを握る位置が大切だと感じることができた。

スムースノズルは、大規模な工場や倉庫が火災になった際、安易に建物の中に入るのは危険なので、屋外から放水する時に使います。
放水が長時間になる時は、管そうを台座に取付け、放水を行うこともできます。
 | 価格:4290円 |
ガンタイプノズルによる放水訓練
私が、消防士長でレスキュー隊の副隊長だった頃の話です。
消防学校の訓練施設で火をおこし、要救助者を救出する訓練を行いました。
消防署の訓練施設では、実際に火をおこすことはできないため貴重な訓練になります。
訓練内容はシンプルで…
私が筒先を担当し、他の隊員2名で人命検索を行うものです。
使用する筒先は「ガンタイプノズル」
私がポンプ車からホースを延長し、燃えている部屋に外から放水をする。
その間に隊員2名は、ライトと命綱の準備をして、空気呼吸器の面体を被る。
私も面体を被り、燃えている部屋に進入開始。
実際に火が見え、熱気も感じられる。
少しでも体勢を高くすれば、首元がヒリヒリと熱い。
低い姿勢を保持し、ストレートの放水をしながら前に進む。
しかし…
なかなか前に進めない。
なぜなら…
放水の圧力が影響しているのは間違いないが、
水が通っているホースが重い。
そのホースを引きずりながら前に進むためだ。
放水圧力とホースをひきずる摩擦との勝負になる。
そして、最も前に進めない要因になるのは、
ホースがドアや家具の隙間に挟まってしまうことだ。
訓練中もその要因が起こる。
全く前に進めなくなった。
直ぐ後ろにいる隊員二人に合図を送る。
「ホースの挟まりを取ってくれ!」
隊員二人が、ドアの隙間に挟まっているホースまで戻り挟まれを取った。
これで上手く前進できる。
放水圧力に耐えながら、ホースの重さ(摩擦)に耐えながら、
10㎝、20㎝と前進していく。
炎の熱気に注意しながら、火元から5mくらいの所まで着たところで…
左手が柔からいものに当たった。
要救助者(ダミー人形)だ。
後ろにいる隊員二人に伝える。
「要救助者発見!」
隊員二人がライトに付いているブザーを1回鳴らし、私はさらに要救助者を超して前に出る。

ライトに付属しているブザーを鳴らすことで、屋外で待機している隊長に「要救助者発見」「救出開始」を知らせることができます。
その間、私は放水を噴霧状に切り替え、要救助者と隊員を熱気から守る。
隊員の一人が要救助者の胸を抱え、一人が足を持つ。
そしてブザーを2回鳴らす。
搬送開始の合図だ。
私は、噴霧注水を継続しながら、隊員が要救助者を搬送するスピードに合わせて後ずさる。
噴霧注水だと放水圧力が軽減されるため、容易に動くことができる。
順調に後ずさる。
そして、屋外に出て、要救助者を救出することができた。
訓練を終えて、ミーティング中に確認されたことは…
燃えている建物の中で円滑に活動するには、筒先担当者が放水しながら前進し、熱気を抑える必要があるということ。
筒先担当者が前進するには、ホースの挟まれなどに早く気づき、その障害を取り除くこと。
これが重要になってくるという結論になった。
「実際の火災現場で活かしていこう」と皆で決意することになった。

放水訓練のエピソードはいかがだったでしょうか?
やはり消防士の活動は、放水なしでは成り立ちません。
放水があるからこそ、人を助けることができるのです。
火災現場で人を助けることができると「消防士になって本当に良かった」と感じることができますよ。
ぜひぜひ消防の世界に!
 | 2026年度版 東京消防庁 科目別・テーマ別過去問題集(消防官1類) [ TAC出版編集部 編 ] 価格:2530円 |
 もとレスキュー隊長の伴走
もとレスキュー隊長の伴走