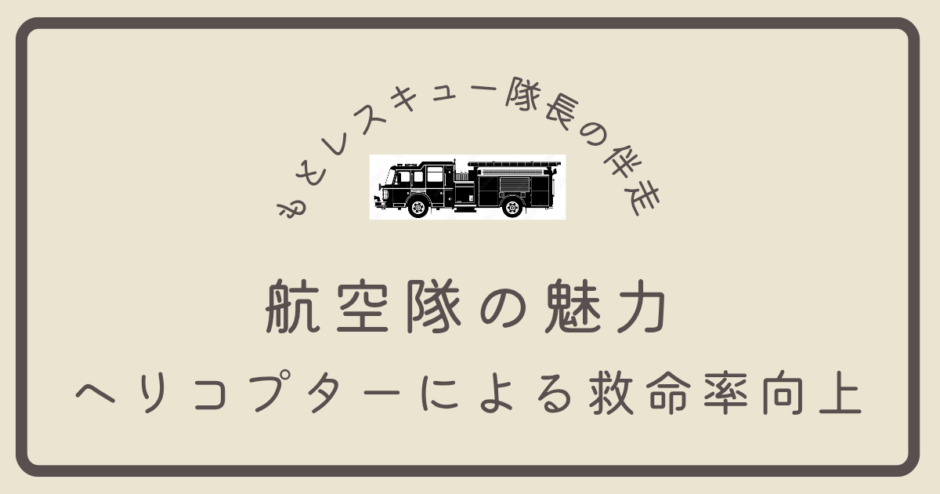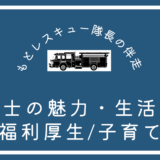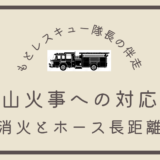消防士になりたい、消防の仕事に興味があるけれど…

航空隊は、どんな災害に行くの?

赤いヘリコプターは、消防のなの?

ヘリコプターから地上に降りる人って決まってるの?

航空隊の隊員は、誰でもなれる?
と想いや悩みを巡らせているのではないでしょうか?
この記事では、これらの想いや悩みを
『東京消防庁もとレスキュー隊長』の『バリー』が今までの経験から解説・アドバイスします。
最後まで読んでいただけたら、東京消防庁・航空隊の魅力がざっくり分かると思います。
ちなみに私は、

消防士は「やりがい」があって最高!
プライベートも充実させてくれて感謝!
って想っている幸せものです。
消防士になりたい、興味がある方にとって、この記事が消防の世界に足を踏み入れる『きっかけ』になってもらえると嬉しいです。
航空救助員
東京消防庁のヘリコプターは、パイロット、整備士、航空救助員が搭乗し、多様な災害に出場します。
高層建物火災や林野火災に対して、消火ヘリコプターとして対応したり…
活動困難な場所からホイスト装置を活用して、人を助けたり…
伊豆諸島などで具合が悪くなった人を救急ヘリコプターとして迅速に病院へ搬送したりしています。

今回の記事は、航空隊の構成を紹介しつつ、航空救助員にスポットを当てて書いていきたいと思います。
航空救助員は、
高層ビルの屋上から、火災で逃げ遅れた人を助けたり…
海で遭難している人を助けたり…
山で遭難している人を助けたり…
川で溺れた人を助けたりします。
災害現場の上空へ飛行し、ホバリングした状態で要救助者のもとに向かいます。
救出の行動手順は以下のとおりです。
【隊員二人進入、ハーネスによる救出の一例】
■機体に設置されたホイスト装置(ワイヤーケーブルを伸長する装置)を整備士が操作。
■整備士は、ホイスト装置のフックを航空救助員の前に差し出す。
■航空救助員二人が着装しているフルボディハーネスのランヤードをワイヤーケーブルのフックに取り付け。
■航空救助員が機体の外に出て、整備士にOKの合図を出す。【隊員二人進入】
■整備士がホイスト装置のワイヤーケーブルを伸長。
■航空救助員二人が宙吊り状態で地上へと降下。
■地上(水面)に降りた航空救助員が『地上到着』の合図を出す。
■航空救助員の1名がホイストワイヤーを保持する。
■もう1名の航空救助員が要救助者と接触し、ハーネスを着装させる。
■ホイストワイヤーのフックに要救助者のハーネスと航空救助員1名のフルボディハーネスのランヤードを取り付ける。
■地上に残る航空救助員が、誘導ロープをホイストワイヤーフックに取り付ける。
■航空救助員が整備士に『ワイヤーケーブル巻取り』の合図を送る。
■整備士がワイヤーケーブルを巻き取る。
■要救助者と航空救助員1名が宙吊り状態で、機体に上昇する。
■宙吊りになった航空救助員は、足首に誘導ロープを巻き付け、回転するのを抑制する。
■機体の真横まで上昇してきた要救助者と航空救助員1名を機体に入れ込む。
■地上に残る航空救助員をホイストワイヤーで引き上げ、病院へと出発する。
この他にも救出の行動手順は、多様にあります。
地上へ降下する航空救助員が3名の場合もあるし、
山岳地帯の救出では、さらに人員が必要であるため、4名から5名の場合もあります。
要救助者の救出で使用するハーネスも要救助者の容態で使い分けたり、
航空救助担架を使用する場合もあります。
このように、航空救助員には、
要救助者がおかれている状況判断
ホイスト降下する技術
要救助者の容態を観察する救急技術
資器材を選定し、取り扱う技術など
高度な判断(知識)や技術が必要になります。
 | 価格:4290円 |
航空隊の構成
東京消防庁の航空隊の基地は、下記のとおり2つに分かれます。
■ 江東航空センター
江東区新木場の東京ヘリポート内にあります。
部隊は、江東飛行隊(操縦士と整備士)と機動救助隊・機動救急隊(航空消防救助機動部隊)で構成されています。
■ 多摩航空センター
立川市泉町の立川飛行場内にあります。
部隊は、多摩飛行隊(操縦士と整備士)と多摩分隊(航空消防救助機動部隊)で構成されています。

操縦士や整備士は、東京消防庁職員採用試験に合格し、専門学校や外部機関へ派遣され国家資格を取得する必要があります。
東京消防庁のヘリコプターは、大型機と中型機に分かれます。
全て赤い機体で、性能等は以下のとおりです。
【大型機】
■こうのとり
全長:19.5m
全幅:16.2m
座席数:22
最大速度:324km/h
航続距離:946km
■はくちょう
全長:19.5m
全幅:16.2m
座席数:22
最大速度:324km/h
航続距離:946km
■ゆりかもめ
全長:19.5m
全幅:16.2m
座席数:23
最大速度:324km/h
航続距離:937km
■ひばり
全長:17.6m
全幅:14.6m
座席数:21
最大速度:313km/h
航続距離:1206km
【中型機】
■かもめ
全長:13.73m
全幅:11.94m
座席数:14
最大速度:277km/h
航続距離:792km
■つばめ
全長:13.73m
全幅:11.94m
座席数:14
最大速度:277km/h
航続距離:792km
■おおたか
全長:13.73m
全幅:11.94m
座席数:13
最大速度:277km/h
航続距離:792km
■ちどり
全長:16.62m
全幅:13.80m
座席数:16
最大速度:306km/h
航続距離:1061km
合計で8機あります。
ヘリコプターには、定期点検や耐空検査などの法定点検が定められているため、それをクリアーした機体が出場体制をとっています。
プロフェッショナル
航空救助員になるには、特別救助技術と救急技術の庁内資格を2つを持つこと、または救急救命士の資格を持っていることが条件になります。
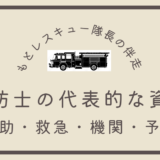 消防士の代表的な資格《救助・救急・機関・予防》
消防士の代表的な資格《救助・救急・機関・予防》
先に話したように航空救助員には高度な知識や技術が必要になります。
要救助者がいる場所は過酷な状況下であることは言うまでもありませんが、そこに降下する人員には限りがあります。
マンパワーが不足する中、要救助者の置かれている状況を把握し、容態を観察しつつ、適正な資器材を選定し、救出する。
航空救助員一人ひとりのレベルが高くなければなりません。
さらに欠かせないのが、現場経験です。
特別救助隊や救急隊として、10年以上の経験を積んでいる隊員がほとんどです。
年齢で言うと、30代後半から40代後半。
航空隊の航空救助員は、正にプロフェッショナルな隊員が選ばれているのです。

私も災害現場で航空救助員と連携して活動した経験があります。
本当にレベルが高く、手際の良さに関心していました。
消防を目指す皆様は、将来的に航空救助員を目標に突き進むのも魅力的な選択の一つになると思います。
ぜひぜひ消防の世界に!
 | 2026年度版 東京消防庁 科目別・テーマ別過去問題集(消防官1類) [ TAC出版編集部 編 ] 価格:2530円 |
 もとレスキュー隊長の伴走
もとレスキュー隊長の伴走