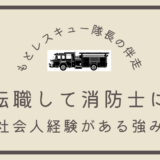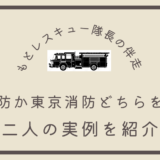消防士になりたい、消防の仕事に興味があるけれど…

訓練って厳しいよね?

三連はしごって何?

訓練のエピソードが知りたいな…
と想いや悩みを巡らせているのではないでしょうか?
この記事では、これらの想いや悩みを
『もと東京消防庁レスキュー隊長』の『バリー』が今までの経験から解説・アドバイスします。
最後まで読んでいただけたら、三連はしごの基礎・訓練の魅力がざっくり分かると思います。
ちなみに私は、

消防士は「やりがい」があって最高!
プライベートも充実させてくれて感謝!
って想っている幸せものです。
消防士になりたい、興味がある方にとって、この記事が消防の世界に足を踏み入れる『きっかけ』になってもらえると嬉しいです。
目次 非表示
人命救助に欠かせない資器材
「三連(さんれん)はしご」… 聞き慣れない言葉だと思います。
消防士になると身近な言葉になります。
東京消防庁では、ほとんどのポンプ車、レスキュー車に積載されていて、災害現場で使う機会が多いからです。
【三連はしごの解説】 写真はこちら
3連式の構造になっていて、収納されている状態・約3mから約9mまで長さを調整できます。(※写真は、約9m伸びている状態です)
はしごに溶接してある滑車にロープが付けられていて、そのロープを引っ張ることで長さを調整することができます。
はしごの下部には、「石づき」という、滑り止めのゴムが2つ付いていて、地面に接地することで安定します。
材質:チタン製
重さ:約32㎏
この三連はしごは、建物3階まで届く長さになるため、火災が発生している建物3階以下の階層窓で逃げ遅れている人を助けることができます。
人命救助には欠かせない資器材です。
ただ、難点があります。
それは、重いということ。
搬送するときは、隊員二人が必要であるし…
使うときは、三連はしごが倒れないように必ず一人が支えていなければなりません。
また、はしごを伸ばす時に使うロープは、しっかり固定する必要があります。
隊員二人の連携と技術が必要になってきます。
この連携と技術を高めるために訓練を行うのです。

三連はしごは、火災現場だけではなく、救助活動現場でも良く使います。
色々な救出方法が確立されています。
今回の記事は、火災現場を想定した「三連はしごを取扱う基本」にフォーカスして解説したいと思います。
搬送する訓練
三連はしごを搬送することも立派な訓練になります。
火災現場では、防火服やズボン、空気呼吸器を着装して活動しますが…
その重さは合計で約19㎏。
三連はしごは32㎏ありますから、搬送するだけで一苦労です。
そのため、隊員二人で息を合わせて搬送しなければなりません。

消防学校では、三連はしごを搬送する訓練があります。
隊員二人の息を合わせて搬送できるようにすること。
完全着装で三連はしごを搬送することで体力を付けること。
が訓練目的になっています。
「完全着装のこと」「個人装備の重さ」について書いた記事がありますので下にリンクを貼っておきますね。
 訓練エピソード①《個人装備の大切さ》
訓練エピソード①《個人装備の大切さ》
 経験から解説《消防士に必要な体力》
経験から解説《消防士に必要な体力》
それでは、消防学校で行う三連はしご搬送訓練を解説していきます。
防火服や空気呼吸器などを完全着装してから訓練スタートです。
隊員二人同時に右肩に担ぎます。(写真はこちら)
この時に右肩に乗せるだけではなく、右腕で三連はしごを体に引きつけます。
進行方向を見て、後方の隊員が「発進準備よし!」と前方の隊員に声をかけ、
前方の隊員は、その声を聞き、「発進!」と声をかけ、進むのです。
《ここで二人の息が合わないと、余計な体力を消耗してしまうし、三連はしごのバランスが崩れて、隊員二人が転倒してしまう危険があります。》
まずは歩いて、三連はしごの重さに慣れていきます。
5分…10分と歩くうち、
右肩に三連はしごの重さがのしかかります。
疲れてくると三連はしごを体に引きつける力を落ちてきて、右肩から外れていきます。
消防学校の教官から、注意を受け、何度も何度も右肩に担ぎなおします。
こうやって、三連はしごの搬送方法を体で覚えていくのです。
20分くらい搬送した頃には、みんなヘトヘトです。
消防士として体力の重要性を思い知らされます。
一旦休憩後、さらにステップアップした搬送訓練をします。
右肩に三連はしごが上手く担ぐことができるようになったので、左手で資器材を持ちます。
前方の隊員が投光器(約11㎏)、後方の隊員が発動発電機(約14㎏)を持つ。
もちろん右肩には、32㎏の三連はしごを担いでいる。
これはかなり重い…
みんな必死になって搬送します。
辛いけど、周りを見ればみんな頑張っている。
そうやって訓練を乗り越えていきます。

火災現場の初期活動は、資器材を搬送することから始まります。
ここで体力をなるべく温存しないといけません。
それには、三連はしごを基本通りに担いで、隊員二人の息を合わせることが大切です。
 | 価格:4290円 |
伸てい・架ていは重要な技術
またまた聞き慣れない言葉だと思います。
「伸(しん)てい」「架(か)てい」と読みます。
ちなみに「てい」は、漢字で「梯」と書きます。
梯は「はしご」と読みますから…
伸ていは、三連はしごを伸ばすこと。
架ていは、三連はしごを窓やベランダに架けること。
を意味します。
この「伸てい」と「架てい」には、技術が必要です。
消防学校では、この技術が身に付くように繰り返し訓練を行います。
消防署でも、この技術力が落ちないよう、訓練を繰り返し行っていきます。
それだけ、重要な技術ということです。
伸てい・架てい訓練
前方にある建物2階の窓に三連はしごを架ていする訓練のスタートです。
「発進準備よし!」「発進!」
建物の前まで来て、後方の隊員が石づきを置く。
それを見た前方の隊員は、「起てい!」(はしごを立てること)と合図を送る。
後方の隊員は、石づきを足の裏で踏み、しっかり地面に固定する。
三連はしごが立ったら…
後方の隊員は、三連はしごを支え、前方の隊員は、ロープの操作をします。
「はしご確保!」(前方の隊員が後方の隊員に三連はしごが倒れないように指示します)
「はしご確保よし!」(後方の隊員が三連はしごをしっかり支え、呼称します)
「はしご伸てい!」(前方の隊員がロープを引くことで、はしごが伸びていきます)
建物2階の窓の高さにはしごが伸びてきたら、ロックを掛けます。

ロープを引いてはしごを伸ばすと、30㎝ごとにロックが掛かる仕組みになっています。
そのため、収納時の長さ3mから9mまでの間で長さを調整することができるのです。
このロックを掛けるときに技術が必要になります。(ロープを引きすぎるとロックが外れてしまいますので、繊細な調整が必要です)
ロックが掛かる部品のことを「掛け金」と言いますので、ロックが掛かるのを確認したら「掛け金よし!」と呼称します。
その後、そのロックが外れないように、ロープで固定します。
三連はしごのロープのことを「引き綱」と言い…
固定することを「結着」(ロープを結ぶこと)と言います。
「掛け金よし!」(しっかりロックが掛かったことを確認します)
「引き綱結着!はしご確保!」(ロープを操作すると三連はしごが揺れるため、しっかり確保させます)
「引き綱結着よし!」(ロープの固定は、〈巻き結び〉という結び方で結着します。)
「はしご架てい!」(建物2階の窓にはしごを架けます)
「はしご架ていよし!」(三連はしごが、登りやすい角度〈約75度〉になっているか確認します)
これで、三連はしごを登って、建物2階に入ることができるのです。
この行動が基本になり、何度も何度もこの行動を繰り返し、どんな建物でも架ていできるように技術を高めていくのです。
まとめ
三連はしごについて、少し理解できたでしょうか?
合図や呼称が「専門的な用語」で難しかったと思います。
ただ、消防士になれば、これらの言葉はすぐに聞き慣れます。
三連はしごは、災害現場で「人命救助」をするために欠かせない資器材だからです。
一方で「重い」ため、搬送する時に体力を消耗したり、はしごが転倒してしまうデメリットもあります。
そのため、繰り返し訓練をして、隊員の連携と技術を高める必要があるのです。

三連はしごの取扱いは、基本行動をすることが技術を高める近道になります。
「重さ」のデメリットは、訓練を繰り返ししていくうちに体力も付き、克服していくことでしょう。
ぜひぜひ消防の世界に!
 | 2026年度版 東京消防庁 科目別・テーマ別過去問題集(消防官1類) [ TAC出版編集部 編 ] 価格:2530円 |
 もとレスキュー隊長の伴走
もとレスキュー隊長の伴走