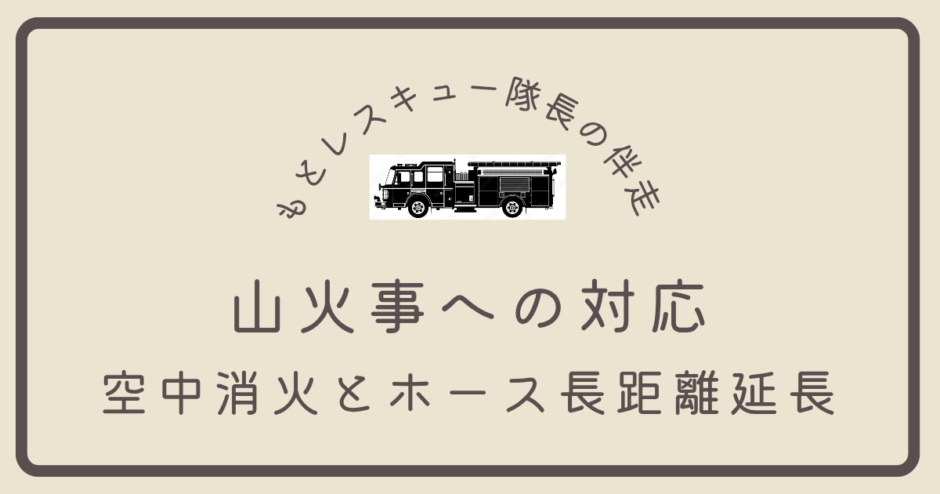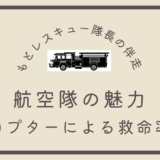消防士になりたい、消防の仕事に興味があるけれど…

山火事を消すのになぜ長時間かかるの?

山火事は夜中も活動するの?

ヘリコプターからもっと水を落とせないの?

雨降っても鎮火にならないのはなぜ?
と想いや悩みを巡らせているのではないでしょうか?
この記事では、これらの想いや悩みを
『東京消防庁もとレスキュー隊長』の『バリー』が今までの経験から解説・アドバイスします。
最後まで読んでいただけたら、消防の山火事対応がざっくり分かると思います。
ちなみに私は、

消防士は「やりがい」があって最高!
プライベートも充実させてくれて感謝!
って想っている幸せものです。
消防士になりたい、興味がある方にとって、この記事が消防の世界に足を踏み入れる『きっかけ』になってもらえると嬉しいです。
目次 非表示
山火事の困難性
消防士にとって忘れてはいけない山火事があります。
1971年に広島県呉市で発生しました。
先行部隊であった21歳から55歳の消防士たち18名が殉職。
大張矢山の中腹で消火活動をしていたところ、突風により吹き上げれれた炎と煙にのまれてしまったのです。
戦後最悪の山火事です。
山火事での消防活動は命懸けです。
私も山火事に出場してきた経験がありますので、その経験も踏まえて、話していきたいと思います。
はじめに、山火事の困難性を見ていきましょう。
■ 風による飛び火
山林の谷に吹く風は、複雑に流れています。
例えば、東の風という情報があっても、尾根や木など地形によって、風の流れが変わります。
火の粉は、この風に乗って飛び火していくので、延焼方向が予測しにくく、消防戦術が立てにくくなります。
■ 急斜面での延焼拡大
乾ききった急斜面に火が付けば、急速に延焼拡大していきます。
特に尾根方向(上方向)への延焼速度は、かなり早いです。
上昇気流にのって、高温で可燃性ガスが含まれた煙によって延焼拡大していくのです。
さらに、その急斜面に消防士がいたのなら、待避するのは至難の技です。
足場が悪く、滑落の危険性があり、落石が降ってくる恐れもあります。
■ 水利不足
消火栓や防火水槽などの水利は、その地域に存在する住宅の割合で設置されています。
山間部では、住宅の数が少ないため、水利も自ずと少なくなります。
それを補うために山によっては、ダイライトタンクなどに水を貯めている消防用水がありますが、大規模な山火事を防ぐほどの水にはなりません。
沢の水を期待して、山に入ったことがありますが、山火事が起きる季節は、降水量が少なく、沢が枯れていることもあります。
■ 夜間活動の制限
山で夜間活動することは、視界が制限され危険要因を見落とす可能性が高く大変危険です。
消防ヘリコプターも同様の理由で夜間の空中消火は実施できないのです。
そのため消防隊は、山には入らず、麓にある民家への延焼を阻止する活動をしています。
また、早朝は風が弱まっていることが多いことから、一挙に鎮圧を試みるため、早朝に備えて作戦を練っている場合もあります。
■ 車両進入や資器材運搬の限界
山への進入ルートは限られています。
そもそも徒歩ルートしかない山もあります。
林道(林業の人が使う砂利道)がある山もありますが、ポンプ車が進入できるような幅員は確保されていないでしょう。
せいぜい軽トラが走行できる程度です。
そうなると、資器材は消防士が持っていかなければなりません。
山火事で持っていける資器材は…
・可搬式ポンプ
・1t程度の折り畳み水槽
・ホース延長用の背負子
・ジェットシューター(水18リットルを背負い、細いホースの先端にあるノズルから水を噴射させる資器材)
ですが…
この資器材で大規模な山火事に対応することは難しいです。
民家やインフラ施設を防御する
山火事で地上からの消火は難しいことが分かってもらえたと思います。
そのため、消防隊は、山の麓にある民家やインフラ施設を守ることを最優先に考えます。
先ほども話しましたが、山間部は水利が少ないため、限られた水利からホースを長距離延長することになります。
例えば、Aポンプ車が消火栓から水を吸い上げ、300m先にいるBポンプ車に水を送る。
Bポンプ車も300m先にあるCポンプ車に水を送る。
Cポンプ車からさらにホースを民家へと伸ばし、延焼阻止をする。
延長したホースの総数は、100本以上になることは当たり前です。
これだけのホースを使うと、放水する圧力も弱くなってしまい、燃え盛る炎と戦うには劣勢になってしまうことが多いです。

東京消防庁のハイパーレスキューは、遠距離で大量の水を送れる「ホース延長車」を保有しています。
海や川から水を吸い上げ、2km先の現場まで毎分8000リットルの水を送ることができます。
ただ、山間部で使用する場合は、水利の少なさ(水量も少ない)や車体の大きさ(全長7.35m、全幅2.5m)から限界がある場合があります。
 | 価格:4290円 |
空中消火が基本
山の麓の民家やインフラ施設に延焼が予想されない場合や延焼防止措置がとられた場合、山に入ることを検討します。
ただ、山に入って火を向かい打つのは危険が伴います。
冒頭で話したように強風に流れた飛び火により、急激に延焼拡大する危険や逃げる際に滑落や落石が発生する可能性があるからです。
これらの困難性を踏まえて消防の戦術は、空中消火が中心になってきます。
消防ヘリコプターが湖・池・海から水を汲み上げ、直接空から山火事に散水します。
【散水目的】
■ 直接燃えている箇所に散水する消火散水
■ 延焼拡大を防ぐ「防火線」設定のための散水
【散水時に使用する資器材】
■ バケット
ヘリコプター機体下部にワイヤーロープで吊るします。
機体の種類により500リットルから1500リットルの水を散水できます。
■ ファイアーアタッカー
ヘリコプター機体下部に取り付ける水タンク。
機体の種類により900リットルから2700リットルの水を散水することができます。

空中消火時のヘリコプター操縦は難しいと聞きます。
消火水により機体の重量が重くなる上、山上空を飛行すると複雑な気流があります。
その中で、ピンポイントで消火水を散水していくことは、高度な操縦技術が必要なのです。
残り火を消すのは消防隊
空中消火や雨によって炎が見えなくなった山での鎮火判定は、慎重になります。
なぜなら、火が完全に消えきっていないことが多いからです。
残り火があれば、また飛び火して再出火してしまう恐れがあります。
残り火があるところは…
木の「幹の中」や「根本」。
特に古い木やもともと枯れていた木は、幹や根本の中が空洞になりやすく、そこに残り火が生じてしまいます。
空から水が落ちてきても直接残り火にかからないのです。
これらの残り火を消すには、消防隊が山に入り消すしかありません。
手順は以下のとおりです。
■ ヘリコプターによる熱源確認
上空から熱画像装置で熱源を見つけ、その箇所をGPS機能を使って消防隊に知らせます。
■ 入山ルートの選定
消防隊は、消火用水が確保できる入山ルートを選定していきます。
■ 水源の確保
ポンプ車、水槽車、可搬ポンプを使用して、できる限り水を山の中に運びます。
山の中では、水槽を設置し水を貯めるなどの活動をします。
■ 消火活動
水槽などから、ジェットシューターに水を入れ、山へと入っていきます。
残り火を見つけたら、ジェットシューターで注水するか、スコップで砂を掛けて消していきます。
このように消防隊は、地道な活動を行っています。
山火事は広範囲に延焼してしまっているので、鎮火判定には、一つ一つ熱源を確認しているため時間を要している訳です。

山火事が発生すれば、空から地上から消防隊が組織を挙げて対応していきます。
大変な活動になりますが、鎮火できた時は住民からも感謝されます。
ぜひぜひ消防の世界に!
 | 2026年度版 東京消防庁 科目別・テーマ別過去問題集(消防官1類) [ TAC出版編集部 編 ] 価格:2530円 |
 もとレスキュー隊長の伴走
もとレスキュー隊長の伴走